〇理科の学習で6種類の距離にある円内にゴムで動く車を止める実験を行いました。子供たちは、どの距離の円の中にでも、車を止めることができる名人になるぞと意欲的に実験に取り組みました。
〇1回ごとの実験結果を見直して次のゴムの長さを考える子供や望ましい結果が出るまで粘り強く取り組む子供が多く見られました。
〇このように、数多くの実験を通してゴムの長さを長くするほど車が動く距離も伸びることを実験で確かめることができました。


〇理科の学習で6種類の距離にある円内にゴムで動く車を止める実験を行いました。子供たちは、どの距離の円の中にでも、車を止めることができる名人になるぞと意欲的に実験に取り組みました。
〇1回ごとの実験結果を見直して次のゴムの長さを考える子供や望ましい結果が出るまで粘り強く取り組む子供が多く見られました。
〇このように、数多くの実験を通してゴムの長さを長くするほど車が動く距離も伸びることを実験で確かめることができました。


全校のみんなで育て、収穫したさつまいもに感謝の気持ちを込めて、「さつまいもさん
ありがとう集会」を行いました。
なかよしグループ毎に、さつまいもについての劇や紙芝居などを発表したり、環境委員
が企画したゲームや、スマイルランチ委員会のさつまいもクイズを楽しんだりしました。
最後に、蒸かしてもらったさつまいもをみんなで食べました。子供たちは「おいしい」
と言いながら、うれしそうにほおばっていました。






5年生の子供たちは、総合的な学習の時間に五箇山ぼべらを広めるための活動をしています。子供一人一人が伝えたい相手と伝えたい内容、伝える方法を決めて取り組んでいます。
11月16日(土)には、五箇山を訪れる県外の方に五箇山ぼべらのおいしさや特徴を知ってほしいと考えた子供たちが、菅沼合掌集落内で五箇山ぼべらの試食会・説明会を行いました。
「ぼくたちが作った五箇山かぼちゃです。」
「この合掌造りの屋根に使われているかやが古くなったものを敷いて栽培します。」
「パンフレットを作りました。あとでゆっくり見てください。」
と積極的に伝えることができました。また、世界各国からのお客さんも訪れていました。
「Hello!」「It’s local pampkin.」「Here you are.」
と英語を使ってコミュニケーションに挑戦する姿も見られました。
「うん!甘いね。」「どうして『ぼべら』っていうの?」
と観光客からの反応があることも、この活動のおもしろさです。子供たちは、学習してきたことを一生懸命に伝えることができました。
今後も子供たちの思いを大切にしながら、学習を進めていきたいと考えています。




11月14日(木)に折口さんによる読み聞かせがありました。
今回は、ノルウェイの昔話「北風に会いに行った少年」でした。
子供たちは初めて聞く話に興味津々でした。
折口さん、ありがとうございました。

6年生の子供たちは、相倉合掌造り集落の奉仕活動を行いました。茅葺き屋根用の茅の株についた枯れ葉や草を取り除き、来春に茅が育ちやすいように手入れを行いました。世界遺産相倉合掌造り財団の中島さんが、株の手入れをする理由や地域の協力で茅の栽培が行われていることを説明してくださいました。子供たちは、活動を通して、「地域のために活動できてよかった」「これからも地域のために活動したい」など、地域を大切にする気持ちを高めていました。







2年生は、生活科の校外学習で上梨、下梨、見座に行きました。
上梨では、ささら編み体験をしました。子供たちは、職人さんに編み方を教わり、要領よく編み上げることができました。自分で作ったささらを使って踊りだす子供もいました。
下梨では、ギター工房を見学しました。木を貼り合せたり、薄く削って磨いたりするなど、たくさんの工程があることを聞き、ギターができるまでの大変さを知りました。
見座では、お寺の見学をしました。内陣と呼ばれる御本尊が安置されている場所を見せていただきました。普段はなかなか見ることができない場所を見せていただき、子供たちは説明を聞きながら感心していました。


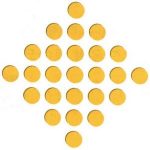
算数科「計算のやくそくを調べよう」の学習で、井口小学校、利賀小学校と遠隔協働学習をしました。
図のドットの数を1つの式に表して求めるために、どのようにまとめたり移動したりして考えたかをタブレットに描き、友達と考えを交流しました。
全員の考えが画面に映し出されると、子供たちは真剣に見ていました。そして、他校の友達の考えを参考にして、問題に取り組む姿が見られました。



昔の人々の生活の工夫を調べるために2学期は五箇山和紙の作り方を学習しています。まず、DVDで作業のあらましを学習しました。すると、子供たちは「本物の和紙や原料や道具を見たい。」「作っている人に工夫を聞きたい。」等の思いをもちました。
そこで、10月10日に東中江和紙生産組合の見学を行いました。子供たちは宮本さんから百年前に作った和紙を見せていただき、五箇山和紙は保存状態がよければ千年もつということを聞いて驚いていました。次に、和紙を作る工程を見学し、和紙をすくまでの間にもたくさんの手間や時間がかかることを知りました。また、働いている方が、ちりとり・紙すき・乾燥の作業を丁寧にして和紙の中に余計なごみや空気が入らないようにたえず確認していらっしゃる姿を見て、子供たちは、「すごく細かいところまで注意しているんだ。」と感心していました。また、五箇山で育てた楮・楮のじくを焼いた灰を使っていることや乾燥に失敗した和紙は水に溶かしてもう一度すくことも知りました。